1. はじめに:血糖値スパイクとは?その危険性と予防の重要性
近年、健康意識の高まりとともに「血糖値スパイク」という言葉を耳にする機会が増えました。血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象を指します。健康な人でも起こりうるこの現象は、単なる一時的な体調不良にとどまらず、長期的に見ると様々な健康リスクを引き起こすことが指摘されています。
血糖値スパイクの定義とメカニズム
食事を摂ると、体内で糖質が分解されてブドウ糖となり、血液中に吸収されて血糖値が上昇します。通常、この血糖値の上昇に対して膵臓からインスリンが分泌され、血糖値は穏やかにコントロールされます。しかし、糖質の多い食事を急いで摂ったり、不規則な食生活を送ったりすると、インスリンの分泌が追いつかず、血糖値が急激に上昇することがあります。これが「血糖値スパイク」です。その後、過剰に分泌されたインスリンによって血糖値は急降下し、低血糖状態になることもあります。
血糖値スパイクが引き起こす健康リスク
血糖値スパイクは、血糖値が気になる方だけでなく、健康な人や血糖値が高めの人にも見られます。この急激な血糖値の変動は、血管の内皮細胞にダメージを与え、酸化ストレスや炎症を引き起こすことが知られています。長期にわたる血糖値スパイクの繰り返しは、以下のような深刻な健康リスクを高める可能性があります。
•生活習慣病のリスク: 膵臓のインスリン分泌機能に負担がかかり、将来的な生活習慣病のリスクを高める可能性があります。
•心血管疾患: 血管へのダメージが蓄積することで、動脈硬化が進行し、心筋梗膜や脳卒中のリスクが増大します。
•がん: 血糖値スパイクによる慢性的な炎症や酸化ストレスは、がん細胞の増殖を促進する可能性が指摘されています。
•認知機能の低下: 脳の血管にもダメージを与えるため、認知症のリスクを高める可能性が示唆されています。
•肥満: 血糖値の急降下による空腹感や倦怠感から、間食や過食に繋がりやすく、肥満の原因となります。
予防の重要性とサプリメントの役割
これらの健康リスクを回避するためには、血糖値スパイクを未然に防ぐことが極めて重要です。食事内容の見直し、規則正しい食生活、適度な運動といった生活習慣の改善が基本となりますが、日々の生活の中でこれらを徹底することは容易ではありません。そこで注目されるのが、血糖値スパイクの予防をサポートするサプリメントです。
サプリメントは、あくまで補助的な役割を果たすものであり、食事や運動といった基本的な生活習慣の改善と併用することで、その効果を最大限に引き出すことができます。本記事では、科学的根拠に基づいた主要なサプリメント成分を徹底的に比較し、具体的な商品推奨や実用的な摂取方法、注意点などを詳しく解説します。血糖値スパイクの予防に関心のある方が、ご自身に合ったサプリメントを見つけ、健康的な生活を送るための一助となることを目指します。
2. 血糖値スパイク予防に役立つ主要サプリメント成分
血糖値スパイクの予防には、様々なメカニズムで糖の吸収を穏やかにしたり、インスリンの働きをサポートしたりする成分が有効です。ここでは、科学的根拠に基づいた主要なサプリメント成分とその作用メカニズムを紹介します。
難消化性デキストリン(食物繊維)
難消化性デキストリンは、トウモロコシデンプンなどを原料とする水溶性食物繊維の一種です。特定保健用食品(トクホ)にも多く利用されており、その名の通り消化されにくい性質を持っています。食事と一緒に摂取することで、小腸での糖の吸収を物理的に遅らせ、食後の血糖値の急激な上昇を穏やかにする効果が期待できます [1]。
作用メカニズム: 難消化性デキストリンは、消化管内でゲル状になり、糖質や脂質を包み込むことで、消化酵素による分解や小腸からの吸収を遅延させます。これにより、食後の血糖値上昇が緩やかになり、インスリンの過剰な分泌を抑えることができます。長期的な摂取により、空腹時血糖値の改善やインスリン必要量の低減にも寄与する可能性が示唆されています [1]。
サラシア
サラシアは、インドやスリランカなどの熱帯地域に自生する植物で、古くからアーユルヴェーダ医学で健康維持のために利用されてきました。その根や幹に含まれるサラシノールなどの成分が、血糖値スパイクの抑制に効果を発揮します [2]。
作用メカニズム: サラシアに含まれる有効成分は、小腸で糖質をブドウ糖に分解する酵素(α-グルコシダーゼ)の働きを阻害します。これにより、糖質の消化吸収が遅延し、食後の血糖値の急激な上昇が抑制されます。近畿大学と小林製薬の共同研究では、サラシアの摂取が食事のたびに繰り返される血糖値スパイクを強く抑制し、高血糖状態の継続を減少させることが確認されています [2]。
ギムネマ
ギムネマは、インド原産のハーブで、「糖を壊すもの」という意味を持つ「ギムネマ・シルベスタ」という学名が示す通り、糖の吸収を抑制する効果が期待されています [3]。
作用メカニズム: ギムネマの葉に含まれるギムネマ酸は、舌の甘味受容体に一時的に結合し、甘味を感じにくくする作用があります。また、小腸での糖の吸収を阻害することで、食後の血糖値上昇を穏やかにします。これにより、インスリンの過剰な分泌を抑え、膵臓への負担を軽減する効果も期待されます。一部の研究では、ギムネマの摂取が血糖コントロールのサポートに寄与する可能性が示されています [3, 4]。
クロム
クロムは、インスリンの働きを助ける必須微量ミネラルであり、糖代謝において重要な役割を担っています。特に、インスリン感受性を高め、細胞がブドウ糖を効率的に利用できるようにすることで、血糖値のコントロールをサポートします [5]。
作用メカニズム: クロムは、インスリン受容体の感受性を高めることで、インスリンがブドウ糖を細胞内に取り込む作用を促進します。これにより、食後の血糖値上昇を穏やかにし、血糖値スパイクの予防に繋がると考えられています。耐糖能異常を持つ患者を対象とした研究では、クロムの補給がブドウ糖消費の改善や血糖コントロールに有益な影響を与える可能性が示唆されています [6]。ただし、全ての研究で一貫した効果が認められているわけではなく、摂取量や形態によっては注意が必要です [7, 8]。
α-リポ酸
α-リポ酸(ALA)は、体内で生成される強力な抗酸化物質であり、エネルギー代謝に深く関わる補酵素です。インスリン感受性の改善や、細胞によるブドウ糖の取り込み促進を通じて、血糖値のコントロールに寄与する可能性が指摘されています [9]。
作用メカニズム: α-リポ酸、特にR-αリポ酸は、グルコーストランスポーター(GLUT4)の細胞膜への移行を促進し、細胞が血液中のブドウ糖を効率的に取り込むのを助けます。これにより、食後の血糖値の急激な上昇を抑え、血糖値スパイクの予防に繋がると考えられます。一部の研究では、α-リポ酸の補給がHbA1cレベルや脂質プロファイルの改善に役立つ可能性が報告されています [10, 11]。しかし、インスリン自己免疫症候群(IAS)などの副作用のリスクも報告されており、摂取には注意が必要です [12]。
バナバ
バナバは、東南アジアに自生する植物で、その葉に含まれるコロソリン酸が血糖値降下作用を持つことで知られています [13]。
作用メカニズム: コロソリン酸は、インスリンと同様に細胞へのブドウ糖の取り込みを促進する作用があります。また、バナバ抽出物は、糖質分解酵素であるα-アミラーゼやα-グルコシダーゼの働きを阻害することで、食事から摂取した糖質の消化吸収を遅らせ、食後の血糖値上昇を穏やかにする効果も期待されています [14]。
桑の葉
桑の葉は、古くから漢方薬として利用されてきた植物で、食後の血糖値上昇を抑制する効果が注目されています。主要な有効成分は、1-デオキシノジリマイシン(1-DNJ)です [15]。
作用メカニズム: 1-DNJは、小腸で糖を分解する酵素(α-グルコシダーゼ)の働きを阻害することで、糖の吸収を遅らせ、食後の急激な血糖値上昇(血糖値スパイク)を抑制します。これにより、インスリンの過剰な分泌を抑え、膵臓への負担を軽減する効果が期待されます。桑の葉粉末や桑の葉由来イミノシュガーの摂取が食後血糖値の上昇を抑制することが複数の研究で報告されています [16, 17]。
3. 具体的な商品推奨:選び方とおすすめサプリメント
血糖値スパイク対策のサプリメントを選ぶ際には、配合されている成分の種類と量、品質、安全性、そして継続しやすい価格帯であるかどうかが重要なポイントとなります。ここでは、主要な成分を配合したおすすめのサプリメントをいくつかご紹介します。
サプリメント選びのポイント
•成分含有量と種類: 科学的根拠が豊富な成分(難消化性デキストリン、サラシア、ギムネマ、桑の葉など)が十分な量配合されているかを確認しましょう。複数の成分を組み合わせることで、より多角的なアプローチが期待できる場合もあります。
•品質と安全性: GMP認定工場で製造されているか、第三者機関による品質チェックが行われているかなど、製品の品質管理体制を確認することが重要です。また、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品は、科学的根拠に基づいた機能性が表示されているため、選択の目安になります。
•継続性: サプリメントは継続して摂取することで効果が期待できるため、無理なく続けられる価格帯であるか、飲みやすい形状であるかなども考慮しましょう。
おすすめサプリメント製品の紹介
以下に、血糖値スパイク対策として人気の高いサプリメントを比較表でご紹介します。
| 製品名 | 主要成分 | 特徴 | 価格(目安) | 購入先(例) |
| 小林製薬 サラシア100 | サラシア由来ネオコタラノール | 特定保健用食品。食事の糖の吸収を穏やかにし、食後血糖値上昇を抑える。手軽なタブレットタイプ。 | 1,752円(約20日分) | Amazon、ドラッグストア |
| 大塚製薬 賢者の食卓 ダブルサポート | 難消化性デキストリン | 特定保健用食品。糖と脂肪の吸収を抑え、食後血糖値・中性脂肪の上昇を穏やかにする。溶けやすい粉末タイプ。 | 1,800円(30包) | Amazon、ドラッグストア |
| 松谷化学 パインファイバーW | 難消化性デキストリン | 特定保健用食品。食後血糖値・中性脂肪の上昇を穏やかにする。飲み物や料理に混ぜやすい粉末タイプ。 | 1,500円(10包) | Amazon、ドラッグストア |
| DHC 血糖値ダブル対策 | ターミナリアベリリカ由来没食子酸、サラシア由来サラシノール | 機能性表示食品。食後の血糖値と中性脂肪の上昇を抑える。複数の成分で多角的にアプローチ。 | 1,500円(30日分) | DHCオンラインストア、ドラッグストア |
| ターミナリアファースト | ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 機能性表示食品。食後の血糖値と中性脂肪の上昇を抑える。糖質や脂質の多い食事を摂りがちな方におすすめ。 | 4,000円(120粒) | 公式サイト、Amazon |
| メタバリアプレミアムEX(富士フイルム) | サラシノール、難消化性デキストリン、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン | 機能性表示食品。糖の吸収を抑え、腸内環境を整える。複数の成分を配合し、総合的にアプローチ。 | 5,000円(240粒) | 公式サイト、ドラッグストア |
| 菊芋サプリ(イヌリン) | イヌリン(水溶性食物繊維) | 食後の血糖値上昇を穏やかにする。腸内環境の改善にも役立つ。 | 1,000円(250g) | Amazon、健康食品店 |
| 桑の葉サプリ | 1-デオキシノジリマイシン(1-DNJ) | 食後の血糖値上昇を抑制。ミネラルや食物繊維も豊富。 | 1,500円(30日分) | ファンケルオンラインストア、ドラッグストア |
組み合わせ摂取の提案
サプリメントは単体で摂取するだけでなく、異なる作用メカニズムを持つ成分を組み合わせることで、より効果的な血糖値スパイク対策が期待できる場合があります。例えば、糖の吸収を物理的に遅らせる難消化性デキストリンと、糖質分解酵素の働きを阻害するサラシアや桑の葉を併用することで、相乗効果が期待できるでしょう。ただし、複数のサプリメントを摂取する際は、成分の重複や過剰摂取に注意し、必要に応じて医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
4. 実用的な摂取方法とタイミング
血糖値スパイクを防ぐサプリメントの効果を最大限に引き出すためには、適切な摂取方法とタイミングが重要です。サプリメントの種類や主成分によって最適な摂取方法は異なりますが、一般的なポイントを以下に示します。
食事との関連性(食前、食中、食後)
多くの血糖値スパイク対策サプリメントは、食後の血糖値上昇を抑えることを目的としているため、食事と同時に、または食事の直前に摂取することが推奨されます。
•食前: 糖の吸収を阻害するタイプの成分(サラシア、ギムネマ、桑の葉など)は、食前に摂取することで、食事から摂取される糖質が小腸で分解・吸収される前に作用し、効果的に血糖値の上昇を穏やかにすることができます。
•食中: 難消化性デキストリンのような水溶性食物繊維は、食事と一緒に摂取することで、食品中の糖質と混ざり合い、消化吸収を遅らせる効果が期待できます。飲み物や料理に混ぜて摂取するタイプが多いです。
•食後: インスリンの働きをサポートする成分(クロム、α-リポ酸など)は、食後に摂取しても効果が期待できますが、食前・食中摂取と組み合わせることで、より総合的なアプローチが可能になります。
1日の摂取量と回数
製品ごとに推奨される1日の摂取量と回数が定められています。必ず製品の表示に従って摂取してください。過剰摂取は効果を高めるどころか、副作用のリスクを高める可能性があります。特に、食後の血糖値上昇を抑える目的のサプリメントは、1日3回の食事に合わせて摂取することが効果的です。
長期的な摂取の考え方
サプリメントは医薬品とは異なり、即効性があるものではありません。血糖値スパイクの予防や体質改善を目指す場合は、数週間から数ヶ月単位で継続して摂取することが重要です。効果を実感するまでには個人差があるため、焦らずに継続することが成功の鍵となります。また、定期的に健康診断などで血糖値の状況を確認し、サプリメントの効果を評価することも大切です。
5. 副作用と注意点:安全な利用のために
血糖値スパイクを防ぐサプリメントは、適切に利用すれば健康維持に役立ちますが、副作用や注意点も存在します。安全に利用するためには、以下の点を理解しておくことが重要です。
各成分の一般的な副作用
•難消化性デキストリン: 大量に摂取すると、お腹の張り、ガス、下痢などの消化器症状を引き起こすことがあります。これは食物繊維の特性によるもので、摂取量を調整することで軽減されることが多いです。
•サラシア: 糖の吸収を阻害する作用があるため、人によっては腹部膨満感、ガス、下痢などの消化器症状を経験することがあります。
•ギムネマ: 糖の吸収を阻害するため、低血糖のリスクがある場合は注意が必要です。また、舌の甘味を感じにくくする作用があるため、味覚に一時的な影響を与えることがあります。
•クロム: 一般的な摂取量では安全とされていますが、過剰摂取は腎臓や肝臓に負担をかける可能性があります。また、一部の研究では発がん性の6価クロムへの変換の可能性も指摘されており、長期的な高用量摂取には注意が必要です [8]。
•α-リポ酸: 稀にインスリン自己免疫症候群(IAS)を引き起こし、低血糖発作を誘発する可能性があります [12]。特に糖尿病治療薬を服用している場合は、医師との相談が必須です。また、胃腸の不快感、吐き気、発疹などの副作用が報告されることもあります。
•バナバ: 血糖降下作用があるため、低血糖のリスクがある場合は注意が必要です。消化器症状を引き起こす可能性も指摘されています。
•桑の葉: 糖の吸収を阻害するため、消化器症状(腹部膨満感、ガス、下痢など)を引き起こすことがあります。低血糖のリスクがある場合も注意が必要です。
薬との相互作用(特に糖尿病治療薬)
血糖値スパイク対策のサプリメントは、血糖値を下げる作用を持つものが多いため、糖尿病治療薬(インスリン製剤、経口血糖降下薬など)と併用すると、低血糖を引き起こす可能性があります。必ず医師や薬剤師に相談し、指示に従って摂取してください。自己判断での併用は非常に危険です。
摂取を避けるべき人
•妊婦・授乳婦: サプリメントの安全性に関する十分なデータがないため、摂取は避けるべきです。
•小児: 同様に安全性に関するデータが不足しているため、摂取は推奨されません。
•特定の疾患を持つ人: 腎臓病、肝臓病、心臓病などの持病がある場合は、サプリメントの成分が病状に影響を与える可能性があるため、必ず医師に相談してください。
•アレルギー体質の人: 原材料を確認し、アレルギーを持つ成分が含まれていないか確認してください。
過剰摂取のリスク
サプリメントは「多く摂れば効果が高まる」というものではありません。製品に記載されている推奨摂取量を守り、過剰摂取は避けてください。過剰摂取は、副作用のリスクを高めるだけでなく、他の栄養素の吸収を阻害したり、健康を害したりする可能性があります。
6. 年代別・目的別の活用法
血糖値スパイク対策のサプリメントは、年代や個人の目的によって活用法が異なります。ご自身のライフスタイルや健康状態に合わせて、効果的にサプリメントを取り入れましょう。
20代~30代:食生活の乱れがちな世代へのアプローチ
この世代は、外食やコンビニ食が多く、糖質過多になりがちな傾向があります。また、仕事やプライベートでのストレスも多く、食生活が不規則になりやすい時期です。血糖値スパイク対策としては、食事の前に糖の吸収を抑えるタイプのサプリメント(サラシア、桑の葉、難消化性デキストリンなど)を積極的に活用し、食後の血糖値上昇を穏やかにすることが有効です。また、運動不足を解消し、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。
40代~50代:生活習慣病リスクが高まる世代へのアプローチ
40代以降は、加齢とともに基礎代謝が低下し、生活習慣病のリスクが高まります。健康診断で血糖値が高めを指摘されることも増える時期です。この世代では、インスリン感受性を高めるクロムやα-リポ酸、糖の吸収を穏やかにするサラシアや難消化性デキストリンなど、複数のアプローチが可能なサプリメントの組み合わせも検討すると良いでしょう。定期的な健康チェックと、食生活・運動習慣の改善を継続することが大切です。
60代以上:加齢による変化とサプリメントの役割
60代以上になると、インスリンの分泌能力や感受性がさらに低下し、血糖値のコントロールが難しくなることがあります。また、複数の疾患を抱えている場合も多く、薬との相互作用にも注意が必要です。この世代では、医師や薬剤師と相談しながら、安全性の高いサプリメント(難消化性デキストリンなど)を選び、少量から始めることをおすすめします。食事のバランスを重視し、無理のない範囲で体を動かすことも重要です。
目的別(ダイエット、健康維持など)
•ダイエット目的: 血糖値スパイクを抑えることで、インスリンの過剰分泌を防ぎ、脂肪の蓄積を抑制する効果が期待できます。特に、糖質制限を意識している場合は、糖の吸収を抑えるサプリメントが役立ちます。ただし、サプリメントだけで痩せることはできないため、食事制限や運動と組み合わせることが必須です。
•健康維持目的: 血糖値スパイクは、自覚症状がないまま血管にダメージを与え続けるため、将来的な疾患予防のために早期からの対策が重要です。特に食後の眠気やだるさを感じやすい方は、血糖値スパイクが起きている可能性があるので、サプリメントの活用を検討してみましょう。
7. 生活習慣との相乗効果:サプリメントを最大限に活かすために
血糖値スパイク対策のサプリメントは、あくまで健康的な生活習慣をサポートするものです。サプリメントの効果を最大限に引き出し、持続的な血糖コントロールを実現するためには、以下の生活習慣との相乗効果を意識することが不可欠です。
食事療法(GI値、糖質制限など)
•低GI食品の選択: GI値(グリセミックインデックス)が低い食品は、食後の血糖値上昇が緩やかです。白米やパンなどの高GI食品を玄米や全粒粉パン、蕎麦などの低GI食品に置き換えることで、血糖値スパイクを抑えることができます。
•食べる順番の工夫: 食事の最初に野菜や海藻類などの食物繊維を摂り、次におかず(タンパク質)、最後に主食(炭水化物)を摂ることで、糖の吸収を穏やかにすることができます。
•糖質量の管理: 極端な糖質制限は推奨されませんが、糖質の摂取量を意識し、過剰な摂取を避けることが重要です。特に、清涼飲料水や菓子類などの加工食品に含まれる糖質には注意が必要です。
•よく噛んでゆっくり食べる: 早食いは血糖値の急上昇を招きます。よく噛んでゆっくり食べることで、満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐとともに、血糖値の上昇を穏やかにすることができます。
運動習慣(食後の軽い運動など)
食後の軽い運動は、血糖値スパイクを抑制するのに非常に効果的です。食後30分~1時間以内に15分程度のウォーキングや軽いストレッチを行うことで、筋肉がブドウ糖を消費し、血糖値の急上昇を抑えることができます。継続的な運動は、インスリン感受性を高め、長期的な血糖コントロールにも寄与します。
睡眠の質
睡眠不足は、インスリン感受性を低下させ、血糖値のコントロールを悪化させることが知られています。質の良い十分な睡眠を確保することは、血糖値スパイクの予防だけでなく、全身の健康維持にも不可欠です。規則正しい睡眠習慣を心がけ、寝室環境を整えましょう。
ストレス管理
ストレスは、血糖値を上昇させるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促進し、血糖値のコントロールを乱す原因となります。適度な休息、趣味、リラクゼーションなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが重要です。ストレスを上手に管理することで、血糖値スパイクのリスクを軽減することができます。
8. 参考文献
1.公益社団法人 福岡県薬剤師会. 難消化性デキストリンには、血糖に対する作用があるか?(一般). https://www.fpa.or.jp/johocenter/yakuji-main/_1635.html
2.近畿大学. 食事のたびに繰り返す血糖値スパイクに対するサラシアの抑制効果を確認. https://www.kindai.ac.jp/news-pr/news-release/2017/05/008255.html
3.高橋クリニック. ギムネマ. https://www.takahashi-clinic.net/tkhadm/wp-content/themes/pc/pdf/supple/93_gymnema.pdf
4.Devangan, S., Varghese, B., Johny, E., & Sreedharan, S. (2021). The effect of Gymnema sylvestre supplementation on glycemic control in type 2 diabetes patients: A systematic review and meta‐analysis. Phytotherapy Research, 35(11), 6033-6045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34467577/
5.Linus Pauling Institute. クロム. https://lpi.oregonstate.edu/jp/mic/%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
6.日本経済新聞社. クロムの補充が糖尿病の改善に役立つのか. https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/hotnews/archives/236506.html
7.Diabetes Care. Chromium Supplementation Does Not Improve Glucose. https://diabetesjournals.org/care/article/28/3/712/27808/Chromium-Supplementation-Does-Not-Improve-Glucose
8.Wiley. マウス細胞内で3価クロムが発がん性の6価クロムに変換されることを発見. https://www.wiley.co.jp/blog/pse/p_33795/
9.Capece, U., Moffa, S., Improta, I., Di Giuseppe, G., & Nista, E. C. (2022). Alpha-Lipoic Acid and Glucose Metabolism: A Comprehensive Update on Biochemical and Therapeutic Features. Nutrients, 15(1), 18. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9824456/
10.Cyclochem Bio. R-αリポ酸の効能とS-αリポ酸の毒性に関する論文の要約と考察. https://www.cyclochem.com/cyclochembio/watch/watch_044_01.html
11.Ghelani, H., Razmovski-Naumovski, V., & Nammi, S. (2017). α‐lipoic acid reduces blood glucose and lipid levels in high‐fat diet and low‐dose streptozotocin‐induced metabolic syndrome and type 2 diabetes in rats. Pharmacology Research & Perspectives, 5(3), e00306. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5464337/
12.独立行政法人 医薬品医療機器総合機構. α-リポ酸 – 「 健康食品 」の安全性・有効性情報. https://hfnet.nibn.go.jp/column/detail4470/
13.Stohs, S. J., Miller, M. J., & Kaats, H. R. (2012). A review of the efficacy and safety of banaba (Lagerstroemia speciosa L.) and its primary active compound corosolic acid. Phytotherapy Research, 26(3), 317-324. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22095937/
14.Synergistic Effect of Banaba Leaf Extract and Policosanol on Glucose and Lipid Metabolism in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. (2023). Molecules, 18(6), 860. https://www.mdpi.com/1424-8247/18/6/860
15.北海道大学. 注目の研究を解説!「腸内細菌に聞く、桑の葉の健康効果」. https://life.sci.hokudai.ac.jp/tl/topic/16601
16.島根県産業技術センター. 桑の葉由来イミノシュガーによる食後血糖値上昇抑制に関する研究. https://www.shimane-iit.jp/files/original/2025042816315816055b4569b.pdf
17.農業・食品産業技術総合研究機構. 血糖値改善物質を高含有する桑葉の製品開発.

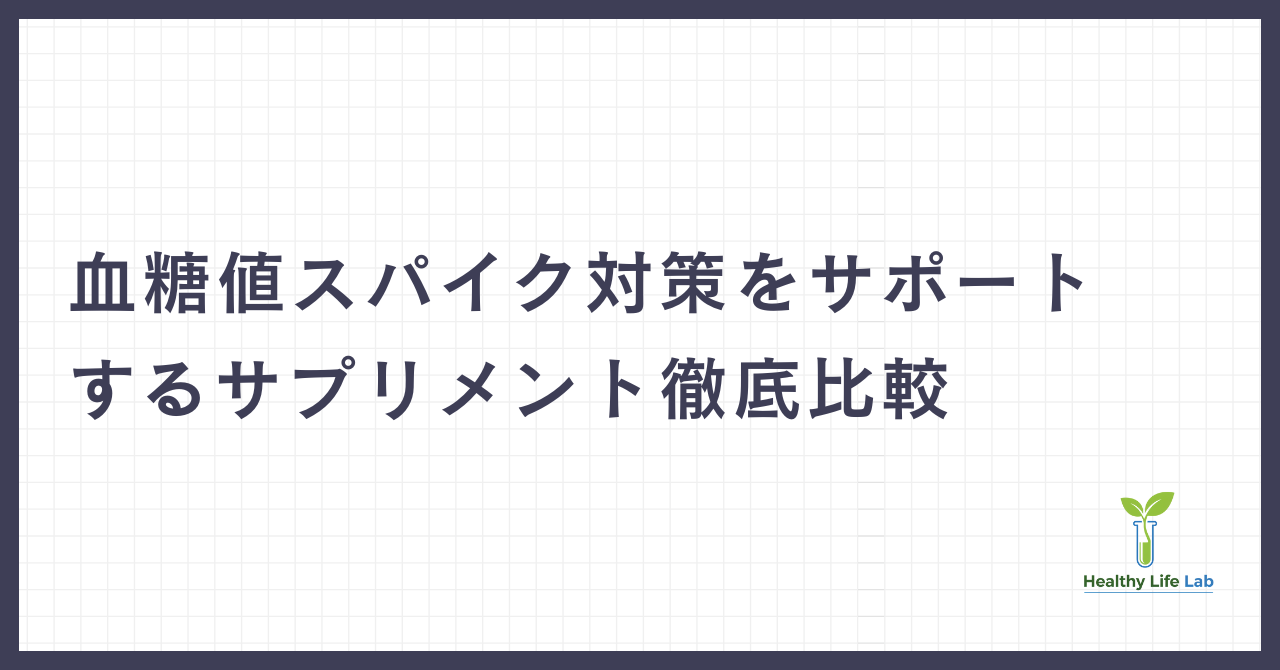
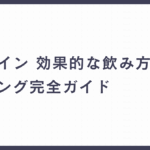
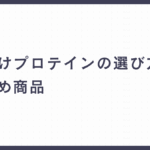
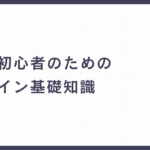
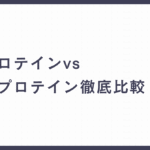
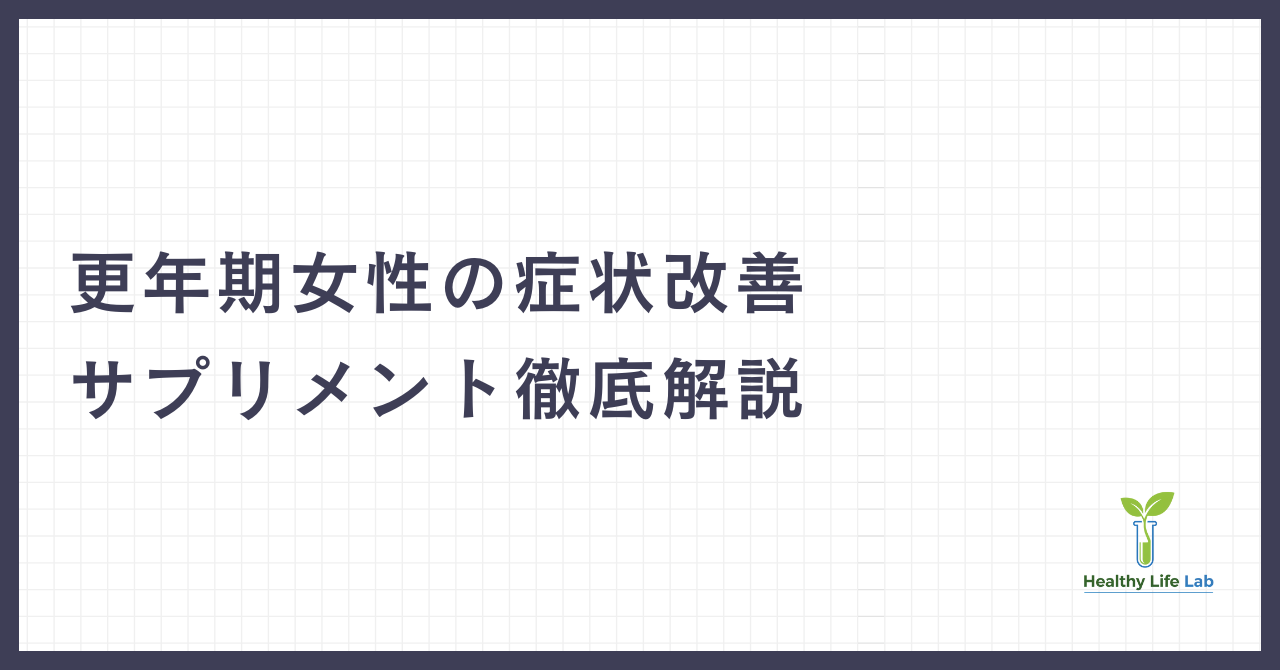
コメントを残す